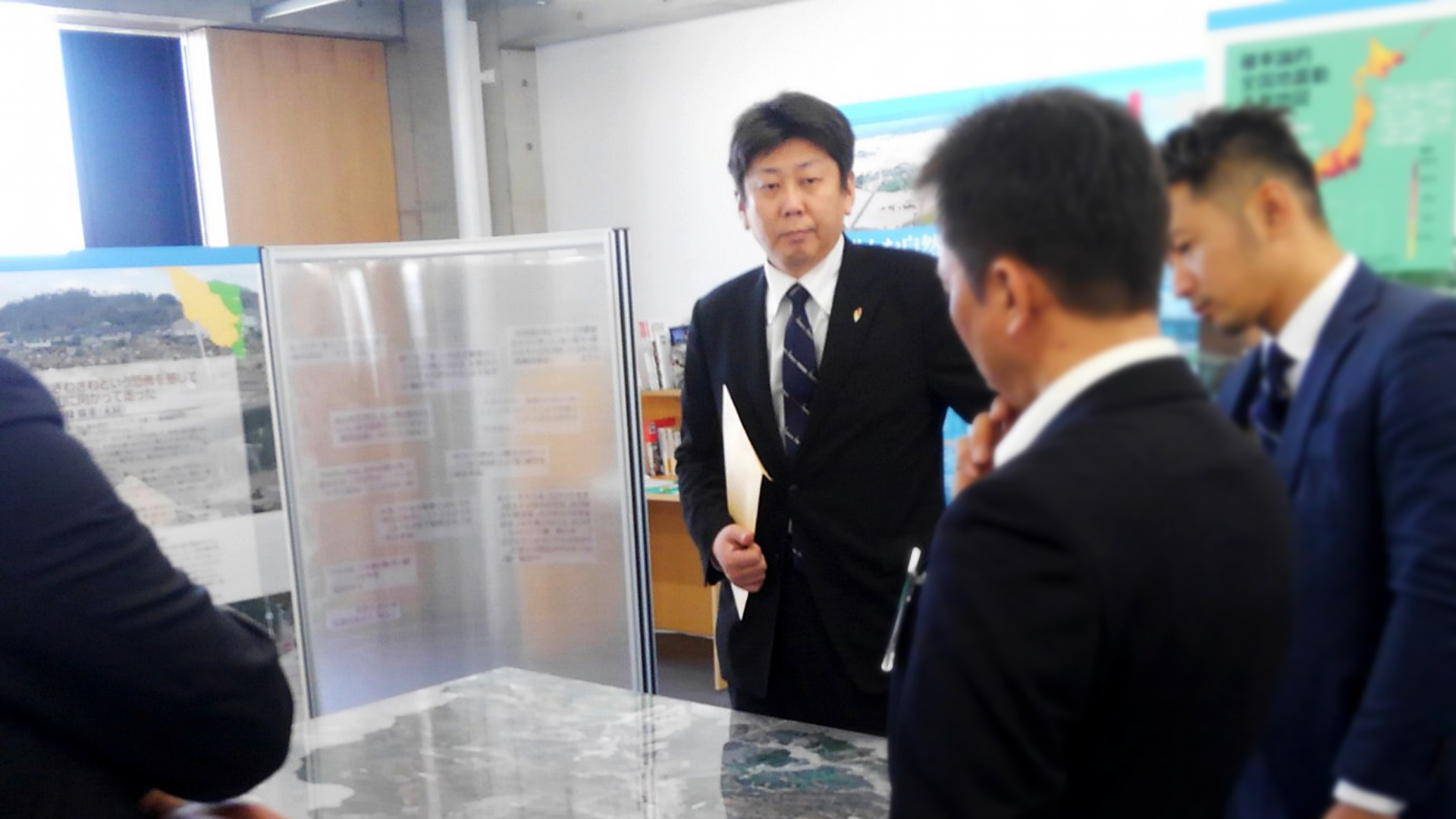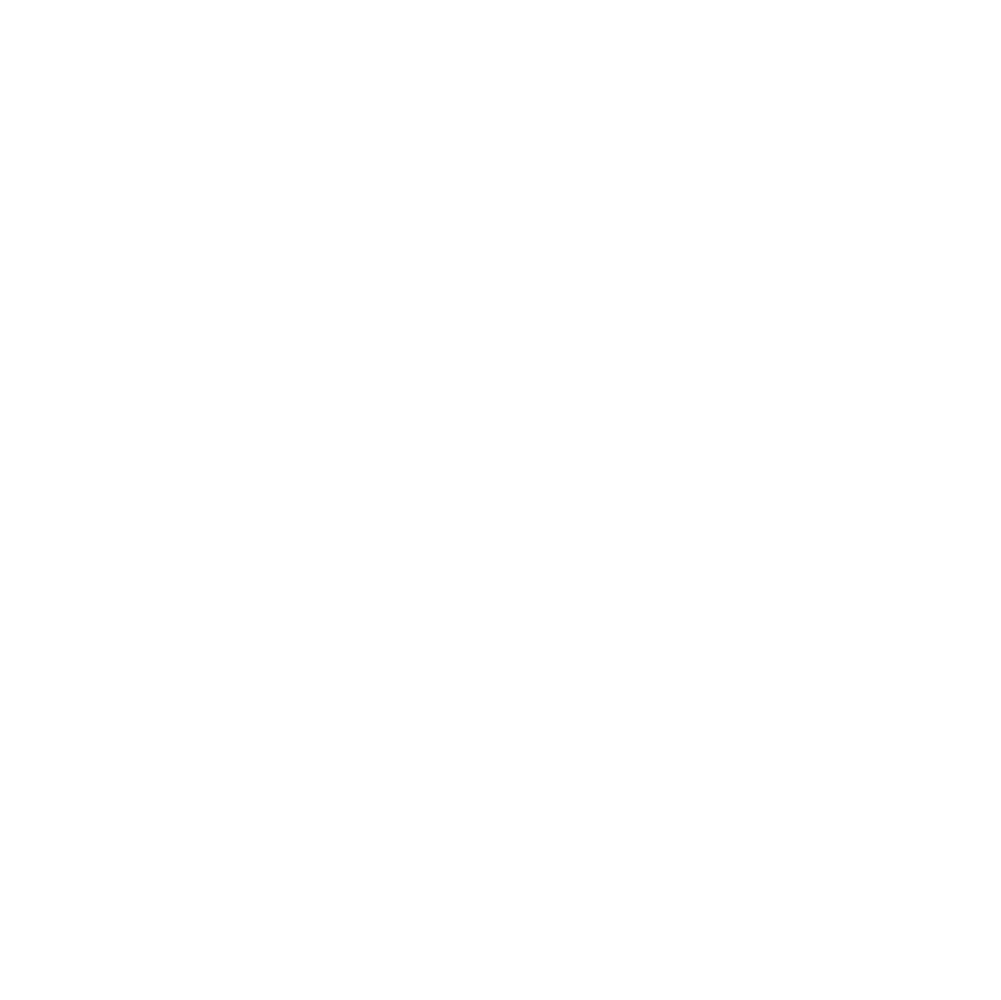地域の未来を創る
Creating the future of the region
激動の経済環境に翻弄される中小企業・小規模事業者
衰退する地方経済
若者は地元を離れ、地方の誇りは薄くなっています
また、景気回復を感じられず、閉塞感が広がり不安を抱く生活が続いています
そんな現状を変え、地域の未来を創るため、みやくぼ大作は全力で頑張ります
ふるさとを守り創る
私達の幼少期40年前は、多くの地域で新年からの左義長(どんど焼き)や、春や秋に開催される獅子舞、夏場の曳山(夜高)や地蔵さんまつり、ラジオ体操に納涼祭や肝試しなどが盛んに行われてきました。子供たちは、知らず知らずに「ふるさと」の匂いを身に着けて育ってきました。現在は少子化により子供数が少ないこともありますが、子供たちに「ふるさと」の匂いを付けるような文化や祭り、町内会の活動が少なくなり、子供たちへ必要な時期にふるさとの匂いを付けてあげられない状況です。このため子供たちは一度外へ出てしまうと帰ってこないのが現状です。すなわち現在の子供たちはふるさとの意味も分からないまま育っています。生まれ育った家はふるさとではありません。今こそ国をあげて危機迫るふるさとを守らなければなりません。
- 地域間の連携を強化し、市町村の枠をこえて「ふるさと」の継承活動の支援
- 商工業者(商工会・商工会議所)を中心に「ふるさと」事業を展開する活動支援
- 「ふるさと」教育を地域コミュニティーと小中学校で連携する活動支援
人を守り創る
現在、国の大きな問題の一つとして、地域の人手不足は大変な状況にあります。地域活動では「ふるさと」事業が衰退し、活動母体の団体等の解散、解体が増えてきています。また中小・小規模事業者も、新卒者採用はおろか中途入社による労働力の確保が難しく、廃業数も増えてきています。しかし地域に目を向ければ就労待機者の多さには驚きます。全国には160万人ともいわれる、ニートやひきこもりの方がいます。また社会に出づらい中であれば障害をお持ちの方は1000万人も居られます。重度の障害をお持ちの方はなかなか社会のつながりは難しいですが、軽度の方であれば350万人おられるそうです。160万人の方と合わせると、なんと500万人を超える方々が社会に出たいけど出られない状況にあります。この状況を改善し、労働者と経営者がWINWINとなる関係を構築することが重要です。
- 相談する場所の整備(商工会・商工会議所)を行い、利用しやすい環境を整える支援
- 就労体験事業を普及し必要な支援を行う
土地を守り創る
国土は日本の大きな財産でありますが、近年急激に、地域において、空き家や空き地、耕作放棄地などが増えてきています。空き家の増加に歯止めがかからない状況で、地域の治安の悪化の傾向にあります。現在住まわれている家もいずれは空き家になる認識をもち、すべての住居者が空き家予備軍の認識が必要です。空き地を手放す際に、外国人に購入される事案が増えてきています。その際に重要なのは、「この町をどうして行くのか」という住民の意思とそのまちづくりの計画です。これは、地域自治体や自治会、商工業者(商工会・商工会議所)が一体となって考えていくことが重要です。今こそ国が土地を利用しやすい環境を整え有効に使うことで、円安や円高など諸外国の影響に左右されない国創りが必要です。
- 地域自治体や自治会、商工業者(商工会・商工会議所)が一体となり、町づくりを計画し実行するための支援を行う

Ⅰ.地域の活力を創る
Create regional vitality
1.人口減少や高齢化に対応した地域の創出
① 就労待機者の雇用創出
生産年齢人口の流出による地元企業の人手不足を解消するために、就労待機者の就労体験からの雇用創出による「未来を見据えた次世代の労働人口の育成」を継続的に実施できる体制を整備し「地域を守って」いきます。
② 健康経営の推進
地元で安心して事業を継続していくことができるよう、中小・小規模事業者の「経営者の健康」と「経営の健康」の「健康経営」実現を目的として、中小企業・小規模事業者支援対策費の大幅拡充を図ります。
2.地域への流入人口の増加推進
① Iターン・Uターンの促進
生産年齢人口の流出による地元企業の人手不足を解消するために、就労待機者の就労体験からの雇用創出による「未来を見据えた次世代の労働人口の育成」を継続的に実施できる体制を整備し「地域を守って」いきます。
② 企業誘致とスタートアップ支援
地域のインフラを整備し、企業が事業を行いやすい環境を整えます。地元企業やベンチャー企業が成長できるよう、商工会等の支援機関とのネットワークや経営支援を提供し、地域に根差した雇用を創出します。
3.起業・事業承継支援
地方の自立した経済基盤の形成には、地域に根差し、サービスの提供者・消費者の役割を担う中小企業・小規模事業者が必要です。独自の技術や知識を次世代に引き継ぐためにも、これまで以上に起業・創業支援、事業承継支援に注力していきます。


Ⅱ.中小・小規模事業者の未来を創る
Shaping the future of SMEs and micro-businesses

1.中小・小規模事業者の価格転嫁の推進
価格転嫁を促進する環境整備
中小・小規模事業者が地元で継続的に事業が行えるように、価格交渉可能な仕組みを作り適切な価格転嫁を促進し、中小企業・小規模事業者が賃上げを図ることができる環境を整備します。
2.事業者の継続的な販路拡大の推進
① マッチング機会の提供
地域資源の活用や農商工連携等により開発された特産品を国内外で普及を後押しするため、中小企業・小規模事業者とバイヤーとのビジネスマッチング等の機会を提供するほか、マーケットイン視点による商品開発・改良に対する支援を強化します。
② 地域産品等の販売会の実施
中小企業・小規模事業者の販路開拓を支援するため、全国規模で商圏拡大を目指す事業者向け販売会を開催し、地域外の消費者やバイヤー等に向けたテストマーケティングや新規取引拡大等を目的としたPRの機会を継続して提供できるように努めます。
③ 日本産品の輸出促進
海外バイヤーや現地流通販売事業者とのネットワークを構築し、現地販売拠点を整備するとともに、展示商談会や商社などを通じた海外販路の拡大支援を行います。また、中小企業・小規模事業者の海外販路への挑戦を円滑なものとするため、駐日外国公館の外交官等を対象に日本の特産品や文化を紹介するイベントを開催する等、将来に向けた海外販路拡大の取組みを支援します。
3.災害対策の強化
① 被災地の支援の継続・強化
東日本大震災や能登半島地震等の自然災害による被災地の風評被害等を払拭するとともに、被災事業者の事業再開・再建に向けた支援を継続します。被害が甚大な場合には、国をあげた商品PRを実施するほか、商品開発・販路開拓支援、観光誘客に関する支援策等を強化します。
② 「罹災証明」の弾力的発行
中小企業・小規模事業者は住家と事業所が一体化した建物で 事業を営んでいることも多く、罹災証明の対象外となります。中小企業・小規模事業者の事業特性を鑑み、住家と事業所が一体化した建物の罹災証明の発行を弾力的に実施できるようにします。
③ 事業者としての支援金制度の創設
事業用資産については、被災者生活再建支援制度の対象外となっています。中小企業・小規模事業者にとっては、被災後、事業 を再開するまでがもっとも負担が大きくなることから、被災した事業用資産を対象とした支援金制度の創設を目指します。
Ⅲ.事業者への支援機能を強化する
Strengthen support functions for businesses

1.各種の支援制度の継続・拡充
① 補助金事業の申請簡素化と内容の見直し
2016年に小規模企業振興基本法が設立されて以降、持続化補助金をはじめ小規模事業者が活用できる施策が充実してきている。しかし、申請手続きの煩雑さは依然として残っており、各施策の内容を思い切って見直し、より使い勝手の良い補助メニューの創出を行います。
② 小規模事業者持続化補助金の継続
新たな需要開拓や生産性向上に資する小規模事業者持続化補助金は事業者の販路開拓・生産性向上に大変寄与しています。同 補助金を今後も継続実施し安定的な財源を確保するとともに、更なる活用推進を図るため、制度内容の簡素化、業種業態の固有の課題に対応した補助メニューの創出等の改善を進めます。
③ 省力化投資補助金の拡充
小規模事業者の人手不足に対応する即効性のある施策として期 待された制度であったが、多くの事業者にとって活用しやすい制度とはなっていないとの声が多く聞こえます。カタログのラインナップの充実に加え、補助上限や補助率の引き上げなどの拡充を図ります。
④ 事業承継・引継ぎ補助金の継続・拡充
第三者承継においては、FA・仲介費用、プラットフォーム利用時のサポート費用等、事業譲渡の過程における費用が障害となるとの声 もあることから、事業承継・引継ぎ補助金の補助下限額の撤廃や補助率の引き上げ等の拡充を図ります。
⑤ 小規模事業者経営改善資金(マル経)等の拡充
コロナ禍を乗り越えた中小企業・小規模事業者の新たな事業展開等に向けた資金需要に対応するとともに、コロナ期に借入が増大 した事業者の条件変更や借換えによる資金繰り緩和等を図ります。
2.事業者の支援ニーズに対応した支援力向上
① 商工会の人手不足の対応
地域経済の衰退を食い止め、多種多様化する事業者の支援ニーズを細やかに対応するため、商工会の支援体制強化は急務である ことから、現状の設置定数の維持、経営指導員の設置定数の見直し、職員の支援環境整備を図ります。また、指導スキルの高い広域指導員による広域的指導体制の整備を推進します。
➁ DX施策へ補助の創設
今まで商工会行ってきた経営指導のその経営支援ノウハウと最新 技術である生成AIを掛け合わせ、経営支援業務の事務作業の効率化の実現などの様々な効果が期待できることから、生成AIを用いた業務ツール導入を推進します。
③ 地域の小規模事業者が学べる場の提供
地域の事業者においては、都市部と比較して「自ら学ぶ機会」が少ないのが現状であり、商工会の若手経営者や女性経営者を対象として、「自らの経営課題」や「地域経済の方向性」等の地域課題を学ぶ機会を提供する環境づくりを行っていきます。
3.地域振興拠点の整備
商工会館の機能強化
商工会館は、中小企業・小規模事業者に対する経営支援の根
幹でありながら、災害時には復旧・復興拠点の最前線として避難所や支援物資の提供場所の役割も果たす等、地域の重要拠点です。
一方、商工会館は、築40年を超え老朽化が顕著で、持てる機能を十分に果たすことが難しくなっており、また、被災地域においては倒壊リスクも高まるなど、迅速な復旧・復興に向け大きな障壁となって
います。
防災・減災の観点や合併による集約化も踏まえ、経営支援を支障なく実施できるよう商工会館の機能維持・強化を図るため、移転・改修・解体等に対する補助を実現します。
プロフィール
Profile
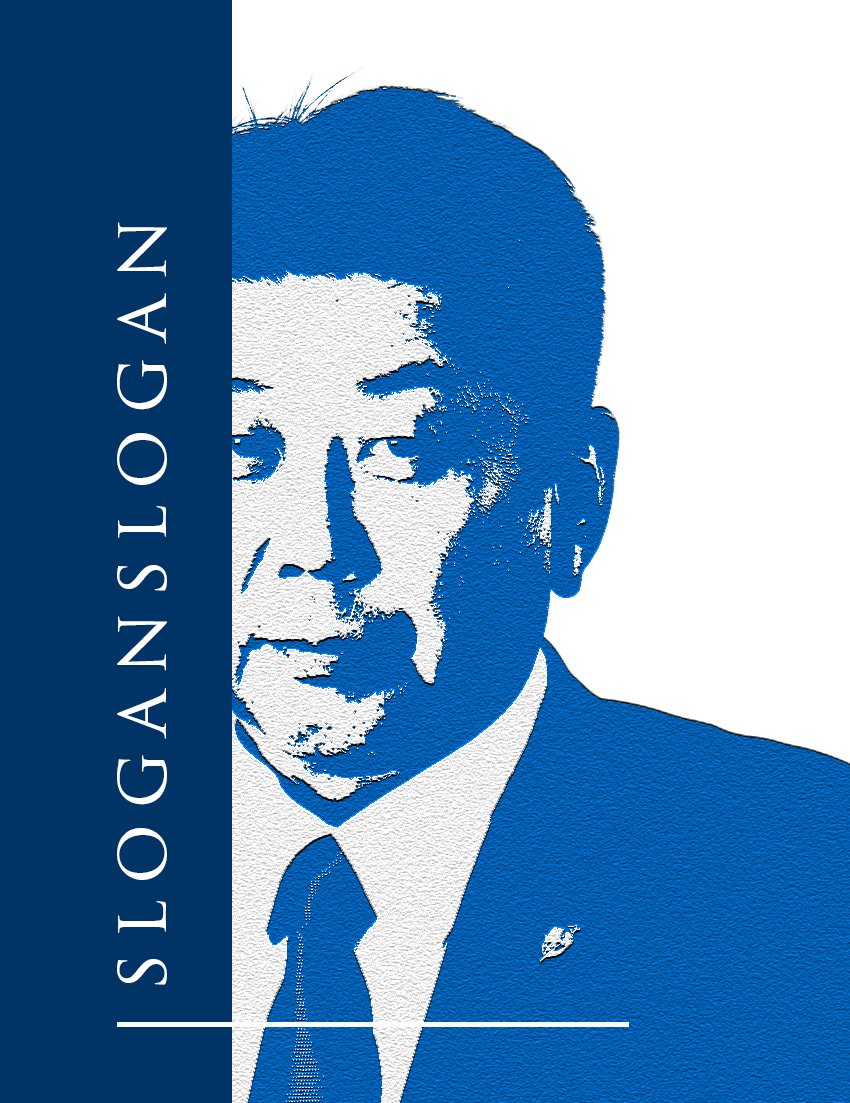
昭和49年10月16日生まれ
富山県庄川町(現 砺波市)
宮窪建設株式会社 代表取締役(一般土木建築工事業)
平成19年に33歳で代表取締役を引き継ぐ
商工会略歴
庄川町商工会理事(工業建設部会長)
平成21年4月~平成23年4月/富山県商工会青年部連合会会長(第18代)
平成23年5月~平成25年5月/全国商工会青年部連合会会長(第19代)
令和5年5月 /全国商工会壮青年部連合会会長(第2代)
令和6年3月 /全国商工会連合会 地域経済再生本部長
主な公職
中小企業庁“ちいさな企業”未来会議コアメンバー(平成23、24年度)
現職
富山県砺波市庄川町東山見地区自治振興会会長
富山県建設専門工事団体協議会会長
一般社団法人日本型枠工事業協会富山県支部支部長
砺波市観光協会理事 他多数
GALLERY









応援にご協力ください
Please Support Us
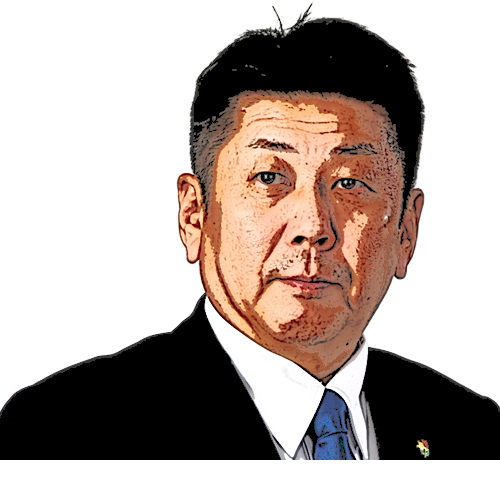
最新情報を発信しています
Social Networking Service
みやくぼ後援会事務所
〒939-1363 富山県砺波市太郎丸6568-1
TEL 0763-55-6821 FAX 0763-55-6822
© miyakubo daisaku 2024